ブログ一覧
-
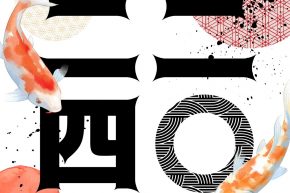 その他 2024.01.01
その他 2024.01.01あけましておめでとうございます!
-
 行事・イベント 2023.12.25
行事・イベント 2023.12.25蔵人サンタのクリスマスプレゼント!
-
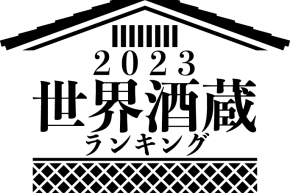 その他 2023.12.11
その他 2023.12.11世界酒蔵ランキング5年連続5つ星受賞達成!!!
-
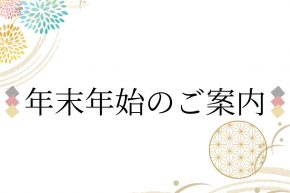 お知らせ 2023.12.05
お知らせ 2023.12.05年末年始の発送予定について
-
 お知らせ 2023.11.25
お知らせ 2023.11.25【重要】オンラインショップ一時閉店のお知らせ。(2時間程度)
-
 その他 2023.11.08
その他 2023.11.082023名古屋国税局長賞受賞!!!!!!!!
-
 その他 2023.11.01
その他 2023.11.01新酒お披露目&杉玉交換をしました✨
-
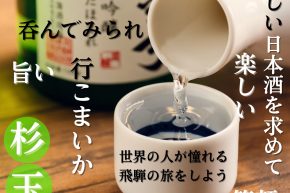 その他 2023.10.18
その他 2023.10.18日本酒イベント!飛騨三蔵まいり★
809件中 9-16件表示
